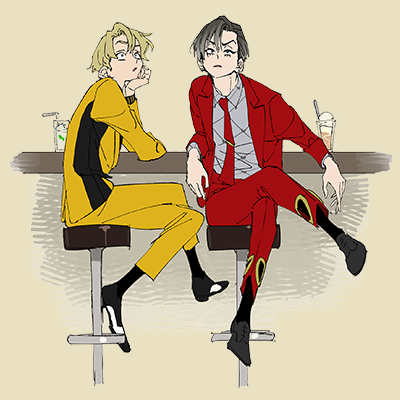SHORT STORY
HIGH CARD Short Story - 001 ミント入りソーダとカフェオレフロート

作:武野光 絵:えびも 絵:れおえん
デスクで書類を整理していると、古式ゆかしい黒電話が今日も鳴った。
「シモンズです」
電話はオールドメイド支店の店内最奥にあり、スポットライトの小さな光に照らされている。この電話を私以外が取ることは無い。
受話器を取ると、電話口から挨拶も無く、要件だけが述べられる。
「承知いたしました。レオ、ウェンディ、ヴィジャイは別件で出ていますので、2人を行かせましょう」
社長直々に掛けてくることがとみに多くなったのは、それだけエクスプレイングカードの収集状況が逼迫しつつあるからだろう。
「そう心配なさらないで。みんな最初はよちよち歩き……日々成長ですよ。見守りましょう」
お前は甘いとたしなめられてから、受話器を置いた。
「さて……彼らは真面目に仕事をしているかな」
「――クリスさん、フィンさん」
扉を開けて車両が展示されているショールームに入ると、トランプのカードが宙を舞っていた。
「たーっ、惜しい! フィン、今の惜しかったよ!」
「おっ、バーナードのじいちゃん! 見て! 今度こそ成功しそうなんだ!」
近頃、クリスはフィンにトランプマジックを仕込むのに熱心だ。彼をおもちゃのように扱っている節もあるが、フィンもまんざらではなさそうだ。つまりは……同性で年齢が近いこともあり、気が合うのだろう。
私は小さく息を吐く。
「お客様がいないからといって遊んでいると、レオ様に叱られますよ。私が告げ口しないとも限りません」
「またまたじいさん、そんなこと言ってぇ」
マスカラで増やしたようなまつ毛の下にある目を艶やかに細めながら、クリスは深紅のスーツの襟を正した。フィンが床のカードを拾い集めて立ち上がる。
「じゃあ、じいちゃん。もう一回やるから見ててくれよ」
「いいえ。見ません」
「お願い! 一回だけ!」
フィンが両手を合わせている。後ろからクリスが彼の頭を押さえるようにして、一緒に頭を下げた。
「お願いです、身寄りのないかわいそうな子なんです。たった一度の晴れ舞台……その目に収めてやってくれませんかっ……」
「身寄りはあるっつーの」
上目遣いで、フィンがクリスにしかめ面を向けている。
私はまた小さく息を吐いた。
「……本当に一度だけですよ」
――結局、フィンが口の中からトランプを吐き出すマジックを見届けた。初めて成功したのかクリスとフィンはハイタッチをして、満足気な顔をしていた。
トランプを片付けさせてから、私はフィンの前に立ち、彼の曲がったネクタイを結び直すために解いた。
「社長から指令です。2人で出動してください」
「今からぁ? なんでいつも急なんだよ」
フィンが眉を寄せると、クリスが言う。
「社長からしたら俺たちは所詮ただの労働力。役に立たなければポイするだけの駒なんだよ」
「そんなひでー奴なのか、社長は?」
「今度詳しく話すよ。俺たちは貴重なプレイヤーなんだから、もっと丁重に扱ってほしいもんだよねぇ」
「軽口はほどほどに。壁に耳ありですよ」
クリスは生返事をしながらチャコールグレーの髪をかき上げた。
「で、指令ってなんだよ。じいちゃん」
フィンは身支度をしてもらう子供さながらに、直立不動のまま視線だけを向けている。結び目を整えてから、ぽんと叩いた。フィンはまだスーツに慣れないのか、窮屈そうに首を動かした。
「マフィアの取引があります。詳細は不明ですが、カードを授受する可能性があるので、調査してきてください」
「マフィアってクロンダイクファミリーか?」
「違います。名のある組織ではないですが……近頃はクロンダイクファミリーの活動が盛んになっているため、その影響で他の組織も動きが活発化しています。安易に暴力に訴えることもあるでしょうから、注意してください」
「フィン。途中でカフェに寄るぞー。俺、今日はキャラメルラテフロートの気分なのよ」
クリスは車のキーを指でくるくると回している。
「あんたの奢りなら行ってもいいぞ」
「なぁんでそんな偉そうなのよ」
私は出口に向かってフィンの背中を軽く押し出した。
「クリスさん。貴方はフィンさんの教育係ですから、しっかり監督してください。それからフィンさん、この前にしたお約束は?」
フィンは立ち止まって頬に指を当てた。
「えーっと……」
「思い出せますか?」
「そうだ! すぐ殴ろうとしない!」
「そうです。よく覚えていましたね」
私が微笑みかけると「へへっ」とフィンは少年っぽい笑みを肩越しに返した。
「ほら行くよ、フィン~」
クリスが扉を半分開いて待っている。
「詳しい指令の内容と地図は送っておきます」
「そんじゃ、行ってくるわ!」
「行ってらっしゃい。寄り道は少しだけですよ」
既に店の外にいたクリスは、背中を向けたまま手を振った。
私はフィンが追いかけていくのを見送った。

クリスに連れられて、俺は支店の駐車場にきた。
「よし、フィン。乗りな。さっさと出発するぞ」
色気の無い黒塗りのセダンを顎でしゃくっている。
「んん? これ、あんたの車じゃなくね?」
「俺の愛車のライカは修理中だ。任務の度にぐちゃぐちゃになるから、ほんと嫌になっちゃうよ」
「へへへ。あんたと一緒じゃねーか」
「言うねー。でもそういう先輩を舐めた態度、嫌いじゃないよ」
するとクリスが何か思い出したような顔をする。
「そうそう。フィン、目をつぶれ」
「はあ? なんでだよ」
「目つき悪っ。まぁ、いーからいーから」
「あ~ん? ンだよ、わけわかんねーな」
大人しく目をつぶった。すると鼻梁と耳に何かが掛けられる。目を開くと視界が黒く染まっていた。
「なにこれ、サングラスか?」
「サプライズプレゼント~♪」
いつの間にかクリスもサングラスをかけていた。
「俺はこんなスカしたもんかけねーぞ」
「あのねぇ、身なりも大事よ? ピノクル社員なんだからさ」
言いながらクリスは一歩下がって、俺の全身を品定めするように見る。
「ふーむ、悪くはない。ほれ、フィン。ポーズして」
「こうか?」
右手の人差し指でサングラスのテンプルを支えて、左手はポケットに入れてみた。
「もっと胸張って。腰を前に出して」
「こう?」
俺を指さしながら、「いいね~」と唇の端を吊りあげた。
「女の子に声かける時はそのポーズでいきな」
「それはおかしいだろ」
「俺が初任給で買った思い出の品だから大事にしてね。ちなみにその日に車に轢かれたからよろしく」
「うげっ。何がよろしくだよ。縁起わりーな」
「気に入らないなら返してよ」
「ヤだよ。もう貰ったんだ」
はいはい、とばかりにクリスは肩をすくめた。
「ほら、出発するぞ。乗った乗った。それとも……俺のエレガントなエスコートが必要か?」
「いらね~」
「さてと……取引が行われるのはこの辺りらしいが」
クリスが運転席でキャラメルラテフロートのストローを咥えている。助手席の俺は瓶のアップルソーダを手に、外を観察していた。2人ともサングラスはかけたままだ。
「おっ。あいつら、あやしーな」
少し離れたところに、5~6人のチンピラがたむろしていた。
「いやぁ……ただのチンピラ集団じゃないの?」
「違うね。俺、ハイカードに入る前はああいう連中とも接点があったんだ。やべー奴らは空気感が違う」
「へー、さすが元ヤンキー」
「俺はヤンキーじゃねーってずっと言ってんだろ」
「自分でヤンキーって言う人も少ないからねぇ」
「ほら見ろ! なんか受け渡ししてる! きっとカードだ! 行こうぜクリス!」
「え~。あんまり近づきすぎるのは危険よ。任務はあくまで調査だしさぁ」
「ンなこと言って取り逃がしたらどーすんだよ! 俺は手柄立てて給料上げてもらいてーんだよ!」
「あっ! こら待ちなさいっ!」
俺はセダンから出た。かったるいことをやる前にカードを奪ってしまえばいい。ポケットに手を入れて、真っ直ぐ歩いていく。
「おい……止まれ。こっちに来るんじゃねえ」
チンピラの一人が睨みつけてきた。
「まーまー、落ち着けって」
「止まれって言ってんだろうが!」
男はずかずかと歩み寄ってきて、俺の胸倉を掴もうとした。それをスウェーして避ける。
「別に事を荒立てたいわけじゃねーって」
すると苛立ったのか目つきを鋭くし、男は間髪入れずに殴りかかってきた。
それもダッキングして避ける。
「てめ……っ! ちょこまかと……!」
男が躍起になってパンチを振り回してきた。その全てを上体の動きで躱していく。左ボディでもぶち込んで悶絶させてやろうかと思ったが、バーナードのじいちゃんとのお約束を思い出して、手はポケットに仕舞ったままにした。
「ありゃ?」
いつの間にか、チンピラたちに囲まれていた。
「お前、どこのもんだ?」
ちょっとやばい状況になった。俺はスーツの内ポケットのエクスプレイングカードに手を伸ばそうとした。
そのとき――視界の端にいた一人の動きを感じた。黒いものを俺に向けている。たぶん、銃だ。
咄嗟に身体を転がして避けようとしたとき──。
銃を構えていた男が呻き声をあげた。
クリスが飛びながら男の頭を両手で捕まえて、膝蹴りをぶち込んでいた。男は吹っ飛んで地面に転がっていく。
「うへぇ、痛そ」
「だーからやめろって言ったでしょ、フィン」
男は、痙攣しながら泡を吹いた。
「ンだぁ!? てめーらァ!」
別のチンピラが銃を抜いて、今度は即座にクリスに発砲した。
激しい炸裂音の直後、クリスは後方にたたらを踏む。
クリスの赤いスーツの腹部に小さな穴が開いていた。血液が音を立てて一瞬噴き出す。そしてクリスは顔を上げると──にやりと笑った。
両手には、甲の部分にハート型の穴が空いた革グローブが着けられていた。
ハートの5──〈カロリーズハイ〉だ。
「なんで!? どてっ腹に当たったのに……!?」
クリスがちちち、と舌を鳴らす。
「俺は不死身の色男……」
カロリーズハイはプレイヤーであるクリスが負ったあらゆるダメージを修復する。銃弾1発くらいではクリスをひるませることもできない。
「こーなっちゃったらしょうがない。フィン、やっちゃって。お前はプレイ禁止ね」
「あぁっ!? なんでだよ!」
俺は別の男が振るったナイフをダッキングで避けてから、頭突きを顎にぶち込んだ。跳ね上がった顔にさらにワンツーからの右フックを叩き込む。
「目立つのは──厳禁ってこと!」
クリスはムエタイ仕込みの肘を右に左に、2連撃で別の男の顔を切り裂く。
チンピラたちを一掃するのに時間はかからなかった。
クリスが右手を胸の前に出すと、グローブが手の中でカードに戻った。
「さてさて……カードはどこかなっと」
俺は地面に伏したチンピラたちの懐を探った。クリスは周囲を見張っている。
すると白い粉の詰まった袋を発見した。麻薬だ。
「けっ。こんなもんをカードと交換する気だったのか」
さらに俺は黒い小さなケースを見つけたので、早速、中身をあらためた。きっとこれがカードで──。
「って……ただの宝石じゃん。カードは?」
すると遠くから、パトカーのサイレンが聞こえてきた。クリスが舌打ちする。
「ちょっと騒ぎすぎたな」
「この宝石……金になるか?」
「馬鹿言ってんじゃないよ! 置いていきなさい! ほら、さっさと逃げるぞ!」

クレイジー8はオールドメイド支店の付近にある老舗のパブだ。かれこれ30年近く前からここで営業しているらしい。
薄暗い店内は木を基調としていて、サーバーの金色が灯りを反射し、いかにもパブらしい雰囲気だ。カウンターの奥では店名のネオンが煌々としている。
「やっほー、マスター。俺、いつものね♪」
クリスがカウンター席に座るや否や、肘をついて、奥にいた店長に声をかけた。ダグラスだ。
「またお前らか」
やたらと大きな図体にスキンヘッド。威圧感は一般人のそれではない。
「とか言ってマスター、俺たちが足しげく通ってくれて嬉しいでしょ。で……フィンは注文どーすんの?」
「ビール」
「未成年でしょ! ノンアルコール!」
「冗談だって。俺はソーダで」
マスターは返事もせずに背を向けて準備を始めた。
クリスはハイスツールの上で、すらりと伸びた脚を組んだ。俺も隣に腰かける。
「フィンは痛いところとか無いか?」
「ああ。パンチしたときにちょっと拳を痛めたけど問題無いよ。あんたは……聞かなくていいか」
「とーぜん♪ ファジーズを食べるまでもないね」
滑るように2枚のコースターが出てくる。そして溢れんばかりに注がれたグラスが、どかっと音を立てて置かれた。
「お前ら、酒も飲まねーくせに来るんじゃねえよ」
一つは、クリスが愛飲しているカフェオレフロートだ。ダグラスは愛想無くすぐに背を向けた。
「あんなこと言いながら、いつもおまけしてくれるんだよね。ほら、今日はフロートがいつもよりデカイぞ。さりげないのがいいよね~」
クリスはストローに薄い唇をつけた。
「ん~、最高だね。ベトナムコーヒーみたいに練乳が入ってんのよ。カロリーが五臓六腑に染み渡るねぇ」
「甘いもんに甘いもん重ねてどーすんだよ」
俺は舌を出して顔を顰めた。そして自分のグラスに口をつけようとして気付いた。
ソーダの中には、気泡がついたストローを囲むように緑の葉っぱがいくつも沈んでいる。それから、グラスの縁にライムが乗っていた。
「なんだこれ。注文と違くねーか」
「ミントじゃん。ヴァージンモヒートだな。これもマスターのサービスだから、ありがたく飲みなさい」
「ヴァ……なんだそれ? ていうか俺、野菜嫌いなんだよ。葉っぱとか全部」
「ミントは野菜じゃないでしょ」
「わかってるよ。飲めばいいんだろ、飲めば」
俺はストローを口で咥えてからマスターを見た。グラスを拭いている最中に、リモコンで天井近くに設置されたテレビの電源を入れた。
「ンン!? なんだこれ、めちゃくちゃウマい! マスター、あんがと!」
マスターはテレビを見たままで、グラスを拭くタオルを軽く上げた。俺はずずっと音がするまで、一気にミント入りソーダを飲み干した。
「おかわり!」
「ゆっくり飲みなさいよ」
「あんたの奢りだろ? 飲み放題じゃん」
「かーっ、なんて厚かましい子なんでしょ。まぁ、いいよ。ところで今日は大活躍だったな。ボクシングも遊びでやってたって言うわりには板についてるな」
「あいつらがトロかっただけだよ。あんたこそ、ムエタイと総合格闘技をやってたんだっけ」
「元々パピーに習ってたけど、ピノクルに入ってからは強制的に徹底して訓練させられたからな。ほんとは汗臭いこと嫌いなのよ、俺は」
「へー、今度俺に教えてくれよ」
「なに、俺と汗臭いことしたいわけ?」
「いちいち気持ち悪いよな、あんた」
『今日の午後、ギヴス通りで──』
テレビの音声が耳に入り、聞き覚えのある通り名に気を取られた。クリスもスツールを回転させてテレビのほうを向く。
『マフィアの集団が何者かに襲撃される事件が起きました。駆けつけた警察によると、マフィア同士の薬物取引に何者かが介入したと見られています。なお取引に使われたのは美術館からの盗品で市場価格は──』
「…………」
「…………」
俺とクリスは顔を見合わせた。
「なあ、クリス……これまずいんじゃねーか? 俺たちのこと、ニュースになったりしねーよな」
ハイカードはピノクル社の秘密組織だ。絶対に正体がバレてはいけないし、事情を知らない者にエクスプレイングカードの存在を知られることもご法度だ。
クリスが額に手首を当て、ため息をつく。
「あの宝石、そんな貴重品だったのか……」
「お、俺は悪くねーぞ! 向こうが先に手ぇ出してきたんだ!」
「……フィン、俺たちは何も知らない。やってない。そうだろ?」
俺はかくかくと首を上下に振った。
「じいさんには何事もなかったと報告しておく。今日は直帰してやり過ごすぞ。あとは時間が解決してくれる。それから念のため言っておくが、レオにだけは勘付かれるなよ」
「……めちゃくちゃ面倒臭いことになりそう」
「それで済んだらいいけどな。あとは祈れ」
クリスがカフェオレフロートを差し出してくる。俺もおかわりのミント入りソーダを持った。
「今日はおつかれさん……」
グラスを合わせると、2人とも手が震えていたために、かちゃかちゃと音が鳴った。