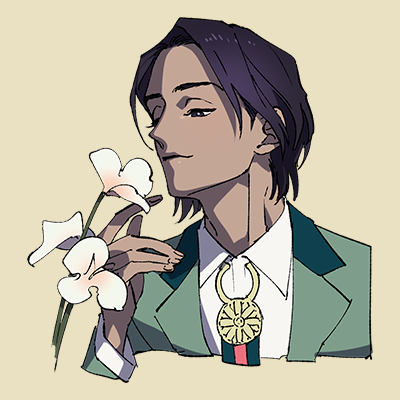SHORT STORY
HIGH CARD Short Story - 002 ヴィジャイのカレー日和

作:武野光 絵:えびも
その日、俺は明け方に目が覚めた。
昨晩は任務があったため興奮していたせいだろうか。やることも無いので、いつもより早くオールドメイド支店に出勤した。
店休日だが、事務作業をすることになっている。始業時間までソファでゴロゴロするつもりだったが、店の入り口を潜ると、ショールームには胃袋を刺激する芳ばしい香りが漂っていた。
「おっ、なんだぁ!? うまそーな匂いする!」
店の奥にはミニキッチンがある。俺はソファにジャケットをぶん投げてドアを開いた。
「じいちゃん! 俺、朝めし食ってねーんだ──」
「私はバーナードさんではありませんよ、フィン」
紫がかったミディアムロングの髪を束ねた、エプロン姿の男が立っていた。ネクタイを締めていない白シャツからは、鎖骨がやけにくっきりと浮いている。
「何してんだ?」
──ヴィジャイ・クマール・シン。ハイカードのメンバーだ。社長の推薦で俺の前に加入したらしい。
「見ての通り、料理ですよ。今日はお客様は来ませんから、皆に昼食を用意しているんです」
ヴィジャイは言いながら、おたまで鍋をゆっくりとかき回す。俺は鍋を覗き込んだ。
「うわっ、カレーだ! なぁなぁ、食っていい?」
「ダメですね。まだ煮込みが足りないので」
すると俺の口元に、ヴィジャイの袖をまくった腕が伸びていた。手の先には焦げ目のついた厚めのクレープ生地のようなものが丸まっている。
「口を開けて」
「なんだよ、俺は子供じゃねーぞ」
「朝食代わりです。味見してください」
深い黒色の瞳を向けてくる。この男はとにかく表情が薄い。何を考えているか分かり辛く、黙っているだけで妙な圧力を感じる。俺は渋々、口を開いて、生地をぱくっと口に入れた。
「……うまっ」
「それはよかった」
笑んだような気がしたが、やはり表情が薄い。
「これ何? ねっちょりしててうまい!」
「チャパティというロティの一種です。タンドールがあればナンのほうが簡単ですが、私の祖国ではこちらのほうが一般的な食べ物です」
「何を言ってるかわかんねーけど、とにかくうまい。もう一口……っていうか1枚ちょーだい」
「構いませんが昼食の分が無くなりますよ」
「レオの分でも減らしとけばいいだろ。子供だし」
「育ち盛りこそ沢山食べるべきですよ。私の朝食のつもりでしたが、こちらをどうぞ。また焼きますから」
「なぁ、肉とか無いの?」
「鶏肉はありますが……これこそ昼食用ですからね。こちらで我慢してください。付け合わせです」
刻んだトマトと紫玉ねぎが和えられたものが入った小皿を出してきた。
「うえっ。それはいらねーや。俺、野菜嫌いなんだ」
するとヴィジャイが目を丸くして俺を凝視した。
「や、野菜が嫌い……? 正気ですか?」
おたまが身体の震えで鍋と干渉して、かたかたと音を鳴らす。怒っているようにも見えた。
「き、嫌いなもんはしょーがねーだろ」
「全部ですか? あらゆる野菜全て?」
「そこまで考えたことねーけど、まぁ、だいたい」
「なんということだ……。クリスは貴方の教育担当ですよね? 彼は何を教えているんです?」
「食生活は業務に関係ねーだろ! ていうかそれなら甘いモンばっか食ってるクリスの指導が先だ!」
「彼はそういう能力ですから致し方がありません。貴方は違うでしょう。ただの食わず嫌いだ」
そこでふと思う。
「能力といえば……あんた植物と話せるってマジ?」
これまでヴィジャイとサシで話したことはあっただろうか。口数の多い男ではない。支店ではシステムを担当しているが、人手が足りなければバーナードのじいちゃんの手伝いや事務の補助、接客もする。要するに支店の便利屋だ。並行して大学で研究活動か何かを行っているらしい。インテリだから、俺はこういう目にでも遭わなければ関わり合いになることは生涯無かっただろう。
「訂正するなら……はっきり会話ができるわけではありません。多少の意志疎通ができるだけです」
ヴィジャイは言いながらコンロのフライパンに、冷蔵庫から取り出したバターの塊と、卵をいくつか割り入れた。
全く言っていることが理解できないが、掘り下げて饒舌に語られても面倒臭い。
「説明されてもわかんねーけど……だからあんたデスクでたまにぶつぶつ喋ってんだな。デスクの観葉植物と──」
「ジャスティンですね」
「はあ? 誰だよ」
「だから彼ですよ。今日、私のデスクにいる彼です。フィンにだって名前があるでしょう」
「今日って……もしかして定期的に変わってんの?」
「貴方は職場にいる人が変わっても気付かないんですか?」
前々から会話の歩調が合わないとは思っていたが、一対一になると、言いようもないむず痒さが強まる。
「でもさ、能力ってプレイ中しか発動しねーだろ。あんた普段から植物……ジャスティン達と話してるだろ。それ能力じゃねーの?」
「はい。できましたよ。これなら口に合うでしょう」
ヴィジャイは炒めていたスクランブルエッグを、フライパンから流れるような手つきで平皿に移した。
「話が終わってねーぞ」
「熱いうちに食べてください。バターをたっぷり使うのが祖国流です」
「めちゃくちゃうまそう」
「では付け合わせにトマトも──」
「それはいらないってば!」
するとショールームのほうから物音がした。
「誰か出勤してきましたね。早く食べて始業してください。ウェンディに指示されていた保険証書の整理は済みましたか? たしか昨日が締め切りでしょう」
「やべっ! あんた、よく人の話聞いてんな~」
俺は図らずも得た朝食プレートにがっついた。

フィンが十代らしい勢いで朝食を平らげるのを見届けてから、私は昼食の準備を続けていた。
間もなく正午に差し掛かろうとしている。私は皆の様子を見るためにミニキッチンからショールームに戻った。
「あ~、もうダメ!」
ウェンディがデスクの椅子で、腕を伸ばしながら大きく背中を反らせている。
「さっきからず~っといい匂いしてるんだもん、こんなの拷問でしょ」
レオがキーボードを打つ手を止めて、ウェンディに鋭い視線を送る。
「おい、時計が読めないのか? まだ昼休憩じゃないだろうが。仕事に集中しろ、減給するぞ」
ウェンディはばつが悪そうに書類に目を落とした。しかし、レオも一瞬、横目でミニキッチンのほうを見ていた。彼も空腹なのだろう。あの年齢で自律して皆をまとめているのだから見上げたものだ。
「お前らホントにヴィジャイのカレーが好きだねぇ」
クリスだ。ソファに身体を沈めながら脚を投げ出し、太ももの上にノートパソコンを置いている。深紅のジャケットはソファにかけ、ネクタイを緩めている。
ウェンディがまた書類から顔を上げた。
「私、ヴィジャイのカレー以外、カレーは食べないようにしてる! 裏切られるから!」
「う~ん。否定できない」
レオがデスクを叩いた。
「だから仕事をしろと言っているだろうが!」
後頭部に腕を回しながら、クリスは私のほうに振り返った。
「先月のやつは格別に良かったよね~。あれなんだっけ? パッパラパッパみたいなやつ」
「パラクパニールですね」
クリスは声を発さずに「それそれ」と口を動かしながら指をさしてきた。私が続ける。
「ほうれん草と白チーズのカレーです。乳製品以外に動物性のものは使用していないので、とてもヘルシーです。調理上のポイントとしては、ほうれん草の緑の鮮やかさを残すため下茹での際に──」
「わ、わかったわかった。そこまで聞いてない」
クリスが苦々しい顔をしながらパソコンに視線を戻す。てっきり興味があるのかと思ったが、どうやら違ったらしい。
すると、クリスの向かい側にいたフィンが勢いよく身体を起こした。両の人差し指だけでキーボードを突っつくようにタイピングしていたせいで、指がそのまま、ぴんと立っている。
「ちょっと待て! まさか今日はその……パッパラパニールじゃねーよな!? 俺、ほうれん草のカレーなんて食えねーぞ!」
額に汗が滲んでいるのは、パソコン作業に慣れていないからだろう。支店に来てから初めて触ったらしい。
私は笑みを投げかける。
「パラクパニールです、フィン。それから、安心して。今日はなんと野菜が無いカレーです。豆類は食べられますか?」
「豆は食える! 気が利くな~、ヴィジャイ!」
「こらぁ、フィン!」
ウェンディがデスクに手をついて立ち上がる。フィンが小さく「うへっ」とつぶやいて肩をすくめる。
「キミね、先輩に対する言葉遣いが──」
クリスが両手を空中でぱたぱたと泳がせる。
「まーまー、ウェンディちゃん。ここはひとつ俺のチャーミングな顔に免じて許してあげて──」
「クリスがちゃんと教育しないから私が代わりに言ってんの! ちょっとレオ、フィンの教育担当、代えたほうが──」
レオも立ち上がった。
「貴様らいい加減にしろ! まだ業務時間中だと言ったよな!? 給料をもらっているんだったら時間までは仕事をしろ──ああっ、12時を回った、クソ!」
「やったぜ! 昼飯だぁ!」
フィンが乱暴にパソコンを閉じて、ミニキッチンに駆けていく。ウェンディとクリスも、顔を見合わせてから早々と追いかけた。
「…………」
レオはデスクで拳を震わせている。
「さ、レオも行きましょう」
「…………」
「切りのいいところまで続けますか?」
「……行く」
わいわいと3人の会話が聞こえてくる。レオも追いかけて行った。
──フィンが来てから、支店は賑やかになった。
クリスは年下の後輩ができて世話好きの一面が見えてきたし、いつも気を張っている努力家のウェンディは表情や言動が柔らかくなった。唯一、レオの血管の耐久性だけが心配だ。
自分のデスクまで移動する。エプロンのポケットからシルバーの霧吹きを取り出し、デスクの隅にあるジャスティンの鉢に何度か水を吹きつけた。
「私は皆の昼食を用意してきます。またあとで」
ミニキッチンに向かう。
ちなみに、フィンには悪いが、今日のカレーは一見すると鶏肉を使ったマサラカレーだが、実際にはたっぷりとミキシングした野菜が入っている。野菜が無いというのは、見かけ上の話だ。
嘘をついたようで心苦しいが、これも彼のため。
少しずつ慣れていってもらおう。
きっといつか、彼も野菜の美味しさに目覚めるに違いないから。